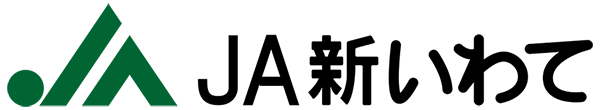農のかたち〜私流〜
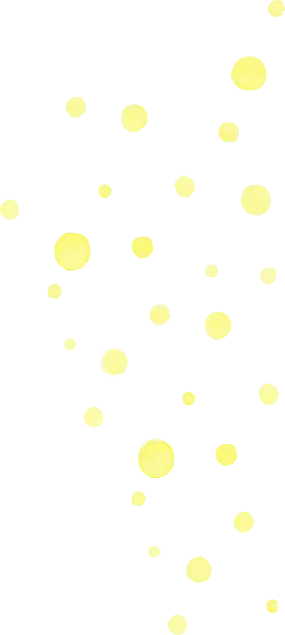
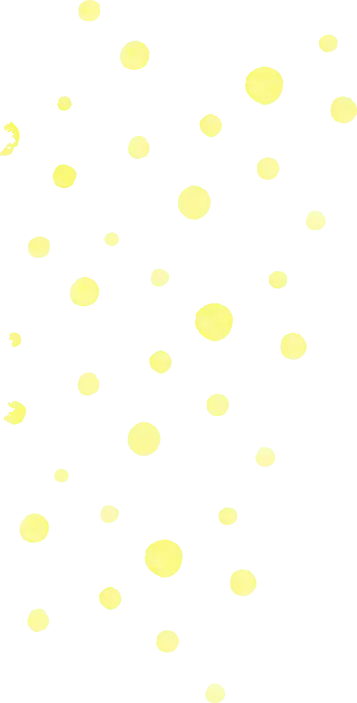
地域の農業を 次の世代に

雫石町で水稲2haと繁殖牛18頭を飼養管理する和人さん。令和2年に祖父から受け継ぎ、当時は1頭だった素牛を18頭まで増頭してきた。就農当時から水稲と大豆とそばを生産する農家やヘルパー組合の仕事も掛け持つことで、水稲栽培や和牛繁殖の知識や技術向上にもつながっている他、人とのつながりが素牛の増頭にもつながっている。
お世話になった方々への恩返しの気持ちを忘れず、地域の農業を未来の子どもたちに繋いでいくため、助け合いながら地域の農業を守っている。
ゼロか100の選択
実家は祖父の代から和牛繁殖と水稲栽培をしていた。長男の和人さんは、子どもの頃から農作業を手伝い、将来は農業をやろうという気持ちを持っていた。一方、祖父や父は農業の傍ら、大工や建設業などの仕事をしている兼業農家だった。「昔から、農業だけでやっていくのは厳しいから手に職を付けていたほうがいいと言われた」と当時を話す。高校卒業後は地元で就職し、外で働きながら実家の農業を手伝う生活をしていた。

父を26歳の時に亡くしていた和人さんだが、令和2年には祖父が亡くなったことで実家の農業を受け継ぐことになった。しかし、当初は3頭いた繁殖牛の素牛は1頭になっていた。牛舎も古く、このまま和牛繁殖はやめるか、経営の核とするかの判断を迫られていた。

「当時、水稲だけでは厳しいと考え、牛をやめないと決めた。結果、必然的に頭数を増やさなければならないという現実もあった」と話す。
農業経営と農家の仕事の二刀流
就農を機に、ヘルパー組合の仕事で和牛繁殖農家の牛の世話や、地元で水稲や大豆などを生産する農家でも働くことにした。「経験や知識も得られればと考えていた」と話し、自らの経営の他に、地元農家でも働く選択をした。そして、この働き方が縁で転機も訪れた。

「外で働くことで人とのつながりが広がった。繁殖牛の増頭を計画するなか、酪農で使っていた牛舎が空くという話しをもらった。おかげで増頭することができた」と笑顔で話す。JAの担当者に相談しながら、血統などを見極めながら自家産も含め15頭を増頭してきた。また、増頭したものの餌となる牧草は足りず購入していた。しかし、地元のソバの生産組合が作付けをやめる畑を紹介され、令和7年から約15haの牧草地を借りることになった。

和人さんは「とても恵まれている」と話し、多くの方に支えられていることに感謝し、「支えてくれた方に、時間はかかるが恩返ししていきたい」と話す。自らの経営はもちろん、地元農家での仕事もあり忙しくはあるが、充実した表情がうかがえる。
また、自らの経験を踏まえ、困っている人と助け合える地域農業の形も模索している。「学校が休みの時には子どもたちも手伝ってくれて、なかでも長女は牛が好きで将来は獣医になりたいと話している。みんなで助け合いながら地域の農業を守り、子どもたちの世代に繋いでいきたい」と話す。子どもたちが笑顔で農業ができる未来を描き始めているようだ。
プロフィール

夷森 和人 さん
※広報誌「夢郷」 2025年2月号掲載時の情報です。掲載情報が変更となっている場合がございます。
このページはお役に立ちましたか?